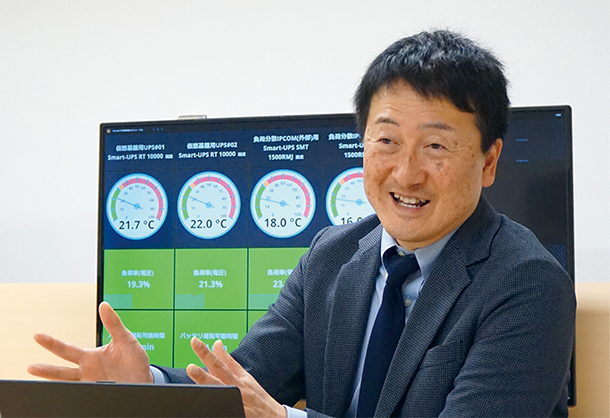公開日:2019/1/16
反復練習を通して、「正しい発音」と「流暢に話す力」を身につける
上智大学
言語教育研究センター
横本 勝也 先生
今回は、『CaLabo EX』を活用する横本先生の「Speaking Foundations」の授業をご紹介する。
この授業では、スピーキングのスキルに特化し、特に新しい表現と発音に注力した指導を展開している。レベルは初級から中級クラス。
授業の目的に合わせた独自のCALL活用
授業は、新しい表現と発音をクラス全員で発声し、確認するところから始まった。毎回新しい表現と発音、また、
ディスカッショントピックが用意されている。次に、ワークシートに沿って、ディスカッションを計4回行う。初めにペアワークを行い、
それから3人のグループワークというように進めていく。さらに、別のディスカッショントピックでペアワーク、3人のグループワークを行う。
横本先生は『CaLabo EX』の「会話機能」でペアやグループ分けをし、次に「ムービーテレコ」を併用し、一斉に録音、回収するという
独自の活用法を生み出している。
「ペアワークやグループワーク中に”会話機能”を使うと、メンバー全員の声が1つの録音ファイルに保存されます。
ディスカッション中に、学生一人ひとりの発音を確認したいときは、ムービーテレコで録音をすると、学生一人ひとりの録音ファイルになるので、
敢えてムービーテレコで録音しています」
横本先生は、スピーキングで重要なのは繰り返し練習することだと語る。そのために、1回の授業で何度もディスカッションを行い、
ペアワークの次にグループワークというように、同じトピックだけれども異なる状況で繰り返し練習できる機会を与え、
学生は90分間常に発話している状態が続く。
ここで、ペアワークの後にグループワークという流れにしているのには何か理由があるのかと尋ねてみた。
「同じペアで繰り返すと飽きてしまいます。また、ペアだと必ず話さなければなりませんが、グループだと1人が話さなくても会話が成立することがあります。
このような状況でも積極的に発言ができるようになるためという狙いがあります」
最後の課題は流暢さのトレーニングだ。表現と発音ばかりを意識しすぎると、流暢さがなくなってしまうので、
このトレーニングも組み入れているという。
「簡単なトピックを与えて、それについて話し続けます。同じトピック、同じ分量で3回に分けて、計6分間話し続けます。
1回目は3分間、2回目は2分間、3回目は1分間というふうに、タイムプレッシャーを増やしていきます。そうすることによって流暢さが上がると言われています」
本来はペアで取り組むものだが、「ムービーテレコ」の一斉録音、回収を活用し、相手に話しかけているような状況を再現している。
時間がペアワークの半分で済むというメリットもあるようだ。今回は、時間の関係で先生の説明にあるような
3段階に分けた6分間のトレーニングはできなかったが、学生は2分間集中して取り組んでいた。
「このトレーニングは家でもできるんです。家での練習のリハーサルにもなるので、スピーキングの練習法の紹介という意味でも行っています。
クラスの限られた時間内だけでは見違えるような効果は見られないけれど、家で継続して同じように取り組めるようになったら、
必ず流暢さが上がる、といつも励ましています」
録音することのメリット
授業中は日本語禁止、英語で話すことを徹底し、毎回必ず録音を行う。
録音をしない普通教室での授業と、録音をするCALL教室での授業では、学生の英語の発話量が圧倒的に違うようだ。
「録音されていると学生の意識が高まり、必然的に英語の発話量が増えることがわかりました。また、録音すると、
机間巡視して聞いただけではカバーしきれない部分まで学生の取り組みを確認できます」と横本先生。
さらに、「発音や文法、紹介した表現を正しく使えているかを個別にフィードバックすると、学生のモチベーションアップとスキルアップにも
繋がるので、録音機能はフル活用しています」と話してくれた。
録音は、先生が学生を評価するためだけのものではない。学生自身が聞き返し、どれだけ向上しているのかを確認するための成果物として
残すことができるので、学習を続けるうえで自分を励ますツールにもなる。
毎回の宿題でも録音は欠かせない。リーディング課題と、その課題に関するトピックが用意されている。
学生はスマートフォン等でそのトピックの回答を録音し、クラウド上の共有フォルダに提出する。日常生活では、
意識をしないと英語を話す機会を持つことが難しいため、宿題でも必ず録音をさせ、英語を話す習慣を身につけるように促している。
初級から中級のクラスとはいえ、ディスカッションも途切れることなく、学生自ら率先して一生懸命取り組んでいる姿が印象深かった。
それは授業中も授業を離れた時でも、英語を使ってほしいという横本先生の熱い思いの表れではないだろうか。