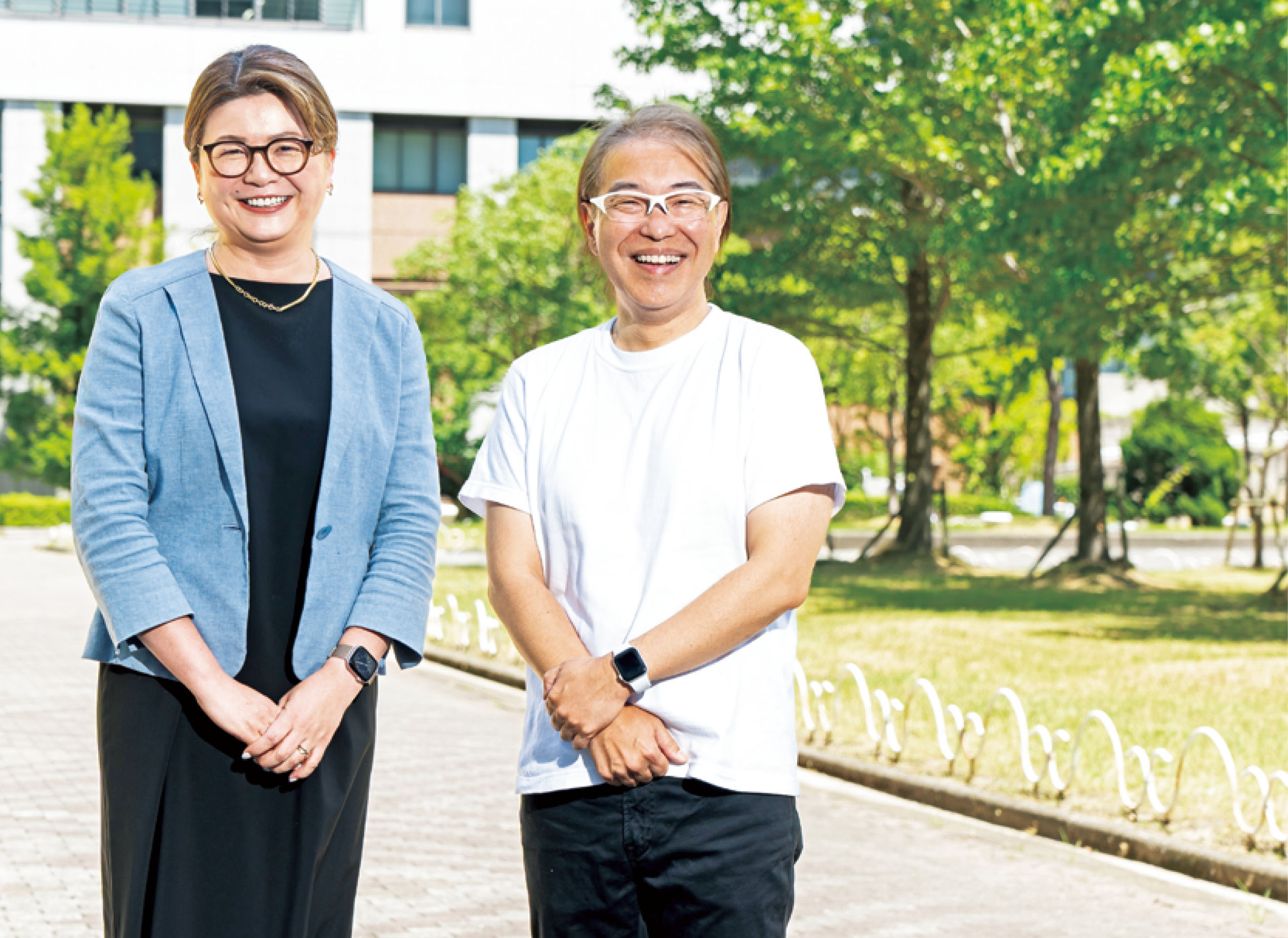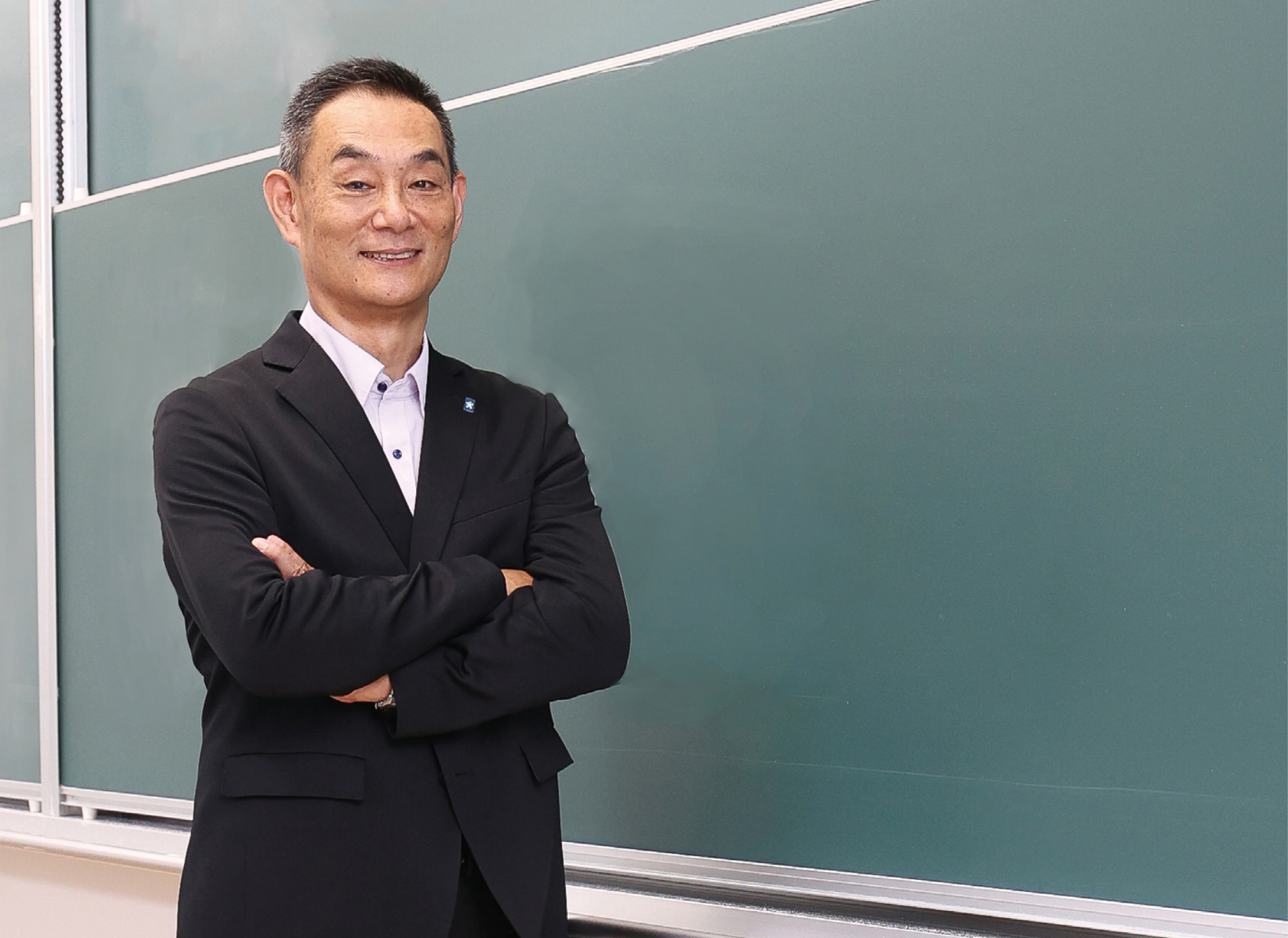公開日:2025/11/3
生成AIなどのメディア活用力を高め個別最適で豊かな学びを実現する
教員養成の今 最新メディアを活用して個別最適な学びを実現できる教員養成
―京都府―
京都教育大学
GIGA端末による1人1台環境が整備され、昨今では生成AIをはじめとする先端テクノロジーが教育現場を大きく変えようとしている。不安の声が先行しがちだが、変化とどう向き合うかを教えることこそ教員の役割だ。京都教育大学「教職キャリア高度化センター」を訪ね、メディアを活用した個別最適で豊かな学びの実現について、大久保紀一朗先生に伺った。


京都教育大学
教職キャリア高度化センター
〒612-8522
京都市伏見区深草藤森町1番地
「教職生活の全体を通じて学び続ける教員」の育成を目的とし、教員養成段階から現職教員のキャリアステージに対応した支援を計画・実施するため、平成30年に設置。
教職キャリア高度化センターの役割
京都教育大学は昭和24年に京都学芸大学として設置され、創立は明治9年の京都府師範学校までさかのぼる。歴史と伝統を誇る教員養成大学として、「人を育てる知の創造と実践を担う大学」を理念に掲げ、高度な専門性と実践力を備えた教員の育成に力を注いでいる。その中核となる組織の一つが「教職キャリア高度化センター」 だ。ここでは、学生を対象とした「教員養成支援」と現職教員を対象とした「教職支援」という2つの役割を持ち、「教職生活の全体を通じて学び続ける教員」を支援することを目的としている。
具体的にはどのような研修やカリキュラムがあるのだろうか。
「学生に対する『教員養成支援』では、就職対策にとどまらず、教職への不安を解消し、キャリア形成を長期的に見据えたアドバイスを行っています。入学した学生の中には強い志を持てずに本学に入学したといった学生もいなくはありません。このような学生が教職の道を自ら選び、長期的なキャリア形成を考えられるよう、継続的な支援を行っています。現職教員を対象とした『教職支援』では、対面やオンライン、オンデマンドなど、ニーズに応じた多様な形で研修を実施しています。特に研修機会が限られる遠方の地域でもオンラインなどで対応できるよう、環境整備を進めてきました。研修内容も、各地域や学校の実情に合わせて柔軟に構成しています。学生から教員までをつなぐ形で、キャリア形成を継続的に支援できる仕組みづくりを目指しています。一度の研修で劇的な変化が起きるとは限りませんが、年に複数回の機会を通じて、変容のきっかけを得ていただけたらと思っています」(大久保紀一朗先生)
「個別最適な学び」を実現するため
授業でのメディア活用力を高める
「教育工学」が専門である大久保先生は特に、メディアを教育にどう取り入れるかをテーマに、研究と実践を重ねている。
「一口に『メディア』といっても、その範囲はとても広いんです。例えば授業では『ドローン』を取り上げて、これからの農業のあり方について考える題材にすることもありますし、『漫画』や『プログラミング』を扱うこともあります」(大久保先生)
こうしたメディアの中でも、教育現場で喫緊の課題として注目されているのが「生成AI」の活用である。大久保先生は、この分野の研究発表もすでに学会などで行っている。これからの教員は、生成AIをどうとらえていくべきなのだろうか?
「教育現場では、学生が生成AIを安易に使ってしまうのではないかという不安もありますが、むしろ多くの学生が慎重に向き合っている姿が見られます。生成AIは、実際に使ってみて初めてその特性や使い方が見えてくるものです。今後は生成AIの活用で思考を深めたり、指導の方法や学びの質をさらに高めたりすることが期待されています」(大久保先生)
生成AIの活用を通じて、教員・学生それぞれの意識にも変化が生まれている。大久保先生は、こうした変化を捉えながら、これからの学びのあり方について、次のように語る。
「今や、インターネットやクラウド、端末といった環境は、学校現場では当たり前になっています。これによって『情報の流れ方』そのものが大きく変わってきました。以前は、情報は教科書や教師などの『情報源』から子供たちに一方向に伝わるものでしたが、今では、子供たちの手元に情報があることが前提になっています。結果、学び方そのものが変化しました。自分に合ったスタイルで学べる『個別最適な学び』や、他者と協働して学ぶ場面が自然に広がってきています」(大久保先生)

学生たちは端末でメモを取り、資料はクラウドで共有。
しなやかで変容できる教員養成を目指したい
このように学校現場の環境が大きく変わっている中、現在の教員養成課程で学ぶ多くの学生は、小学校・中学校時代にクラウドや生成AIに触れてきていない。こうした背景を踏まえ、大久保先生の講義では、積極的に端末活用・クラウドの活用を促している。具体的には、当日の講義内容の事前共有や資料の配付のためにGoogle Classroomを活用したり、グループディスカッションで意見の整理や共有に活用する資料をGoogle スライド™ で作成したりしている。
「先進地域の小学校・中学校で行われていることをこの講義内で実際に体験してもらうことで、教員になった時にスムーズにこのような活動ができると考えています」(大久保先生)
また、講義の最後には「本日のふりかえり」を、Google フォームを活用して提出する形としている。「Google フォームで提出をさせると、グループディスカッションではあまり話していなかった学生がとても興味深いコメントを書いてくれることもあります」と語る大久保先生。提出した結果については、次回の講義の冒頭にいくつか取り上げその場でコメントを返すようにしており、双方向の講義になるように設計されている。
さらに、講義の時間中では生成AIの積極的な活用を促している。
「学生の中には生成AIの活用に後ろ向きな学生がいます。講義の中で使用を促し、どのような回答が来るのか、どのように使ったらいいのかを学生と対話をしながら進めることで、学生たちが生成AIに対してバランスの取れた視点を持てるよう工夫しています。生成AIの活用は一部の中学校で実践が始まったばかりではありますが、教員を目指す今の学生たちは、活用することが当たり前になっていくと思っています」(大久保先生)
そのため、大久保先生は学生たちが近い将来自らが教壇に立つ際に想定される授業スタイルを体験できるようにしているのだ。
最後に、これからの教員養成のあり方について伺った。
「今後もメディアやテクノロジーの変化に合わせ、その時々で豊かに、しなやかに変わり続けられる教員を育てていきたいと思っています。まずは教員自身が学びを楽しみ、自ら変わる経験をして、それを子供たちに伝えてくれたら、こんなに嬉しいことはありません」(大久保先生)
しなやかで変容できる教員養成への取り組みはまだまだ続く。